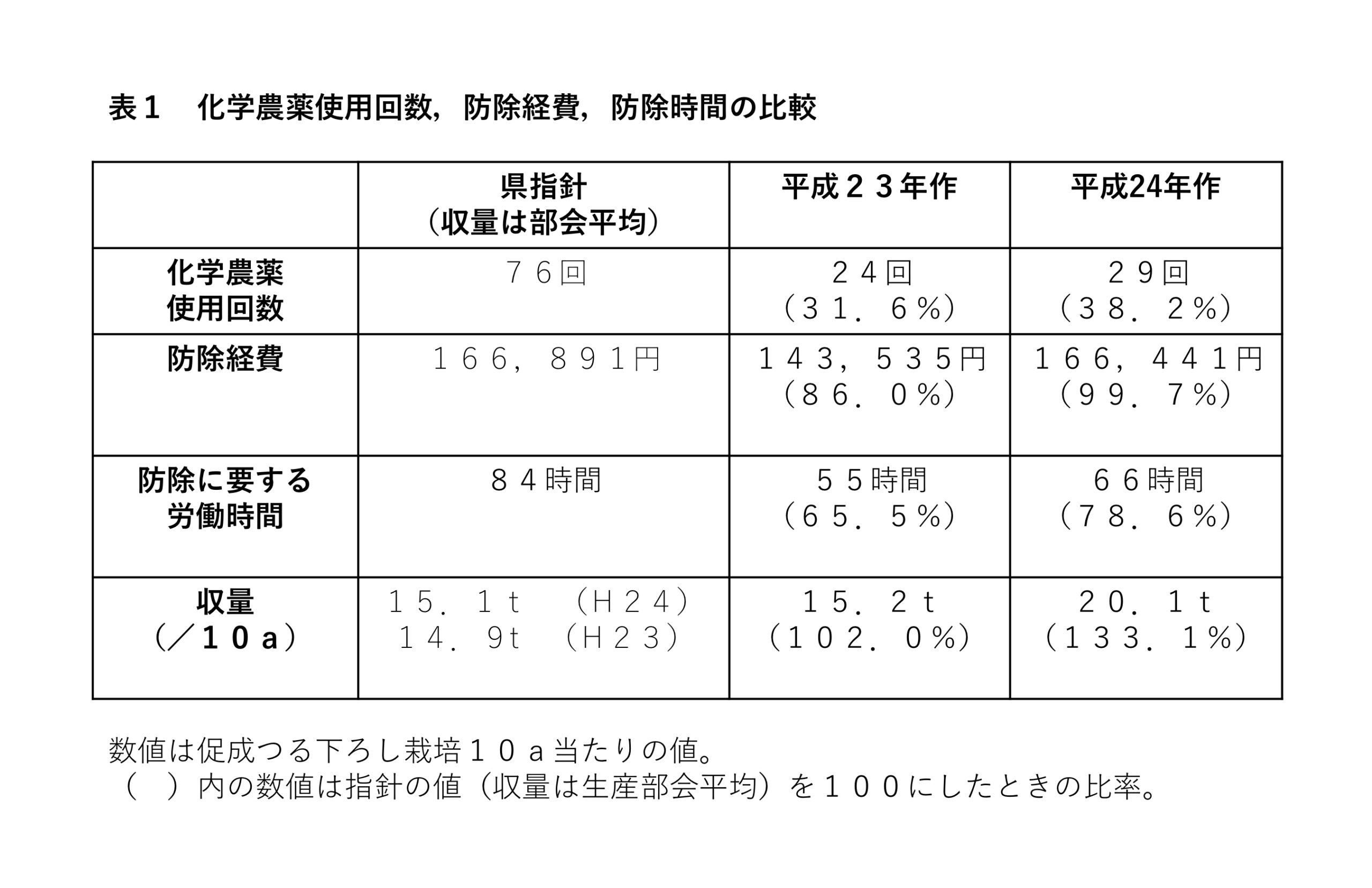黒木 修一
はじめに
8号において、施設キュウリにおける害虫の総合防除について紹介した(1) 。今号では、病害の総合防除について紹介する。
耕種的防除法のポイント
病害の総合的防除も、害虫の総合防除と同様に様々な防除法を組み合わせて行う。太陽熱等を用いて土壌や資材を消毒する物理的防除法や、農薬を使用する化学的防除法、微生物農薬を用いる生物的防除法、そして耕種的防除法の4つの防除法を合理的に組み合わせることになる。
このうち、耕種的防除法には、病害抵抗性品種の利用や作型の変更などがあり、適正施肥や栽培管理も有効な方法である。栽培ほ場全体を見たときに、病害が蔓延している状況で1株だけ発病しなかったり、逆に1株だけ激しく発病していることがある(図1)。これは、栽培管理は病害管理に深く関わっていることを示している。適切な土づくりや、施肥、かん水、整枝剪定など栽培管理の観点から意識して病害防除を考えるべきである。総合的病害虫雑草管理(IPM: Integrated Pest Management)だけでなく、総合的作物管理(ICM: Integrated Crop Management)にも留意する必要がある(2)。
病害対策のタイミング
促成栽培(秋・冬を経て春に向かう作型)は、多くの場合、施設で暖房しつつ栽培される。しかし、外気温が中途半端に低いと、密閉施設で暖房機が作動しないため、湿った空気が滞留して病害が発生しやすい。このため、ベと病、褐斑病、つる枯病、菌核病、灰色かび病などの高湿度を好む病害が発生しやすくなり、薬剤防除が必要となる。
11月ごろの最初の収穫最盛期や、年を越して日長が長くなり地温も上がってくる2月の収量増加期には草勢が低下し、うどんこ病が発生しやすい。追肥など草勢対策を含めた対応が必要となる。キュウリ栽培では気象条件と着果負担に伴う草勢低下が病害発生の重要な要因となる。
総合防除は準備で決まる
病害防除に関しても、害虫防除と同様に、いったん栽培を開始すると、その後の防除は手段が限られてくるので、次作までの準備期間中に耕種的・物理的防除法のうち実施できるものを怠らず実施する必要がある。
施設を被覆する最近のビニールには、流滴(りゅうてき:水のぼた落ちを防ぐこと)や防霧(ぼうむ:施設内に霧が発生するのを防ぐこと)のような機能があり(図2)、これらの機能は気づきにくいが、送風設備による結露防止効果とともに施設内の高湿度環境や植物の濡れを軽減し、病害防除に貢献している。ただし、内側に使用する資材は複数年使用することが多く、汚れていることがあり(図3)、支柱なども同様である。例えば、キュウリ褐斑病は資材に付着したカビの胞子が有力な伝染源となり、次作の病害発生の原因となることが知られている(3)。資材を複数年使用する場合には洗浄したり、太陽熱土壌消毒を行うときに同時に消毒してから使用するなどの対策が必要である。
栽培期間中の防除
栽培期間中は定期的に殺菌剤を使用する。特に苗床時と定植直後は、集中した化学的・生物的防除が重要である。定植前後にマンゼブ水和剤、摘心前後にベと病予防剤、11月初旬にプロシミドン水和剤を散布するほか、毎月1回銅剤やTPN水和剤を施用し、微生物農薬であるバチルス・ズブチリス水和剤を継続的に暖房機のダクト送風を利用して散布する(図4)。ただし、バチルス・ズブチリス水和剤にはダクト散布できる剤とできない剤があるので注意が必要である。これが基幹防除と呼ばれる定期的な予防であり、草勢を適切に管理していれば、これだけでも病害が多発することはなくなる。あとは臨機防除として草勢の低下や気象に合わせて発生病害に登録のある薬剤を施用する。